1.はじめに
仙台を拠点にして散策してきました。
宿舎は、友人の妹君が別荘として使っているマンションです。京都から東京
までに散らばっている友人6人が集合しました。往復の交通は、各人の都合
に合わせて別々、昼間の観光も各人の好みで自由行動、という気楽な集まり
です。どんな発見があるのか、楽しみな4日間でした。
2.神戸空港
関西から仙台に行くには、新幹線、高速バス(京都発の仙台行きあり)、
フェリー(名古屋から)、飛行機などがあります。
私は往復とも飛行機にしました。
.jpg)
飛行機にした理由は、神戸空港です。
今年(2006年)2月16日開港の空
港を覗いておきたい、と思ったためです。
←神戸空港マリンエア
↓幼稚園の子供たち
.jpg)
JRの最寄り駅は三宮で、三宮から空港までは無人運転のポートライナー
で20分でした。滋賀県からのアクセスは割合スムーズです。
航空券はインターネットで予約しました。28日以前予約割引+チケットレ
ス割引で、片道11,100円でした。意外なことに、名古屋空港からより
も、神戸からの方が片道100円安いのでした。
3.青葉城址
仙台空港からバスでJR仙台駅まで40分でした。
この日は青葉城址を訪ねる予定だったため、仙台駅の案内所で尋ねたところ、
「ループル仙台」というレトロ調のバスが巡回していることが分かりました。
.jpg)
ループル仙台は、晩翠草堂から始まる
市内の観光スポットを、一周1時間で巡
回しています。1回250円、1日乗り
放題は600円です。
←ループル仙台
↓晩翠草堂(晩翠が晩年を過ごした家)
.jpg)
青葉城は、関が原の後に60万石に封ぜられた伊達政宗が築いた城です。
現在、城はなく、城址だけです。
本丸の石垣は、ヨーロッパの城壁などに見られるように、四角に加工された
石で隙間なく積み上げられていました。「最近仙台市が修復した」旨の案内
を見かけたので、つまらないことをするものだ、と一挙に興ざめしました。
.jpg)
しかし、修復作業の展示現場の担当者に聞いた
ところ、この石垣は昔からの石を、そのまま積み
直しただけなのだそうです。
←伊達政宗の像
↓加工された石を積み上げた石垣
.jpg)
城跡の公園には、土井晩翠の像がありました。
「荒城の月」の作詞者として名高い晩翠は、明治4年(1871年)に仙台で
生まれ、昭和27年(1952年)に晩翠草堂で亡くなりました。
.jpg) ←土井晩翠像
←土井晩翠像
島﨑藤村の詩碑がありました。
明治5年(1872年)生まれの藤村は、明治
29年(1896年)、25歳のときに東北学園
へ英語教師として赴任し、「草枕」の詩を書き上
げたそうです。
↓藤村の詩碑
.jpg)
青葉城址は青葉山の上にあり、名前のように青葉に囲まれていました。
上空から眺めたら壮観だろうと思いました。
.jpg)
そこで、清水から飛び降りる思いでヘ
リコプターをチャーターし、上を飛んで
みました。左端に上の写真の石垣が見え
ます。
チャーター費用はどれ位か、など興味
のある方は
こちら をご覧ください。
↑上空から見た青葉城址
青葉城址を見学した後、友人3人と仙台駅で合流しました。
京都と名古屋からの友人はフェリー、東京からは新幹線で来ました。合流し
た後、人気のあるホルモン焼き屋に行き、店の外で1時間待ちました。
腹ごしらえをした後、4人でゲームを楽しみました。
4.銀山温泉
翌日、私は友人に会うため、一人で山形県の尾花沢市に行きました。
仙台から新庄行きの48ライナーという特急バスが出ていました。48号線
を走るバスです。バスの最前列に座って景色を眺めていたら、あっという間
に1時間50分が過ぎて尾花沢に着きました。
バス停で友人が待っていました。
私が東京で勤務したときの友人で、40年振りの再会です。友人の家はバス
停のすぐ近くでした。仙台は涼しかったのに、ここはむっとする暑さでした。
「山形は暑いんだよ。ここは冬には2-3メートル雪が積もるしね」と友人
は東京にいたときよりもやや強い東北弁で言いました。
友人が連れて行ってくれたのは銀山温泉です。
.jpg)
ここは江戸時代の初期に銀山として栄え、
寛文11年(1671年)頃に閉山となった後、
温泉地として発展してきたそうです。
←手掘りの坑道跡
.jpg)
温厚な友人は土地の開発事業などにも関わっ
てきたため、顔が広い様子でした。
友人が親しくしている土産物屋さんに入って
みると、昔の温泉街を撮った写真が掲載されて
いました。
 .jpg) ←大正時代の温泉街(江戸屋さん掲示)
↓現在の温泉街
←大正時代の温泉街(江戸屋さん掲示)
↓現在の温泉街
.jpg)
.jpg)
銀山温泉は、木造3階建ての旅館が有名です。
かつては「おしん」のロケ地として、近年はアメ
リカ人女将(ジニーさん)が知名度を上げるのに
寄与しています。
←木造3階建ての旅館
↓アメリカ人女将の旅館(建替え中)
.jpg)
友人は不動産関係の仕事をし、地道に自分の居場所を固めてきたようです。
山形の蕎麦膳をご馳走になり、温泉で汗を流しました。
家族と友人宛にさくらんぼの宅配を手配して、仙台に戻りました。
夕食を済ませてからマンションに戻ると、名古屋からは飛行機、横浜から
は新幹線で、友人が二人来ており、熱戦が進行していました。
5.石巻(いしのまき)
今回は6人が合流しましたが、夜以外は全員で行動することはありません。
ご開帳となる夜だけがコアタイムで、昼は自由です。
翌日、2人は山形へさくらんぼ狩り、私を含む4人は石巻へ出かけました。
.jpg)
松島を横目にしながら、JRで約1時間半で
石巻へ着きました。
←松島の一部(電車から)
.jpg)
石巻には、萬画家石ノ森章太郎さん
の「石ノ森萬画館」があり、萬画の国
をうたい文句にしています。
(「萬画」とは、ジャンルを問わない
作品を量産した石ノ森さんの造語で、
「漫画」を越えた表現ツールである、
という意味のようです)
←JR石巻駅
石ノ森さんの生家がある登米市(中田町石森)は、石巻の少し北です。
(なぜ石巻が張り切っているのかは分かりません)
関西は梅雨空がぐずついていたのに対し、私たちを迎えくれた東北は晴れ
が続きました。とりわけこの日は雲ひとつない快晴でした。
しかし、この日の行程は、テポドンを打ち込まれた以上に悲惨でした。
この日の目的は、石巻漁港にある食堂で新鮮な海鮮料理を食べることでした
が、着いたのが漁港の食堂としては少し遅かったため、めぼしい料理はすべ
て売り切れだったのです。今回の仕切り役は、賭○で生計を立てている組長
です。この組長は、麻雀や碁で、私のような善良な市民からなけなしの小銭
を巻き上げて生活の足しにしている悪役です。
その組長が、朝ドラ見たさに出発時間を遅らせたのが原因でした。
その上、足の悪い仲間にお構いなくスタスタと先導した組長が道を間違え
たため、漁港の周りで往復1時間以上も炎天下を歩かされました。名古屋か
ら来た一人は膝と腰の痛みに顔をゆがめていましたが、帰ってからは病院通
いをしているとのことです。
この日は石巻へ往復し、ありきたりの定食を食べただけで終わりました。
6.秋保(あきう)温泉
翌4日目の最終日の朝、3人は所用で帰りました。
残ったのは組長と、組長の指示通りに忠実に動いたり、ときには組長に強く
意見をしたりする若頭(還暦間近)と、私の3人です。
この日は、年寄りらしくおとなしく温泉に浸かって過ごそう、ということに
なりました。
.jpg)
仙台からバスで1時間ほどの近距離に、秋保
(あきう)温泉があります。
かつて、伊達家の湯治場が置かれたそうで、
有馬、道後とともに、日本三名湯のひとつに数
えられているそうです。
←名取川
.jpg)
自然公園のある湯に陣取りました。
露天風呂付きの温泉に浸かった後は、ゆ
ったりと蕎麦を楽しむことができます。
(食事と入浴のセットで1,575円)
.jpg)
.jpg)
灯篭あり
岩の間を走る水あり
.jpg)
足湯あり(2箇所)
.jpg)
広い池あり
.jpg)
いくつもの花園あり、..。ゆっくり見てまわるのには30分以上はかか
りそうな、広い起伏のある庭園が広がっていました。
いつも碁盤を抱えてくる組長ですが、この日は手ぶらでした。
この日の朝帰った1人は組長の先輩で、日本棋院6段の猛者であるため、い
つものような元気を失くしたのかも知れません。
7.おわりに
杜の都と呼ばれている仙台は、緑一杯に包まれていました。
周囲の山々だけでなく、あちこちの街路樹の緑が街を包みこんでいます。
緑を見て気付いたのは、松、杉、檜などの針葉樹が見当たらず、ほとんどが
欅などの広葉樹だということです。
.jpg)
青葉城址からバスで仙台駅に戻るとき、街路
樹が道路を覆っている光景に感動し、思わずバ
スを降りてしまいました。
いつだったか、ドイツのデュッセルドルフを
歩いたときの感動が蘇ってきたのです。
道路が欅のような巨木の緑に包まれ、ゆったり
とベンチに憩う人の姿が印象的でした。
←定禅寺通りの街路樹
2004年に「景観法」が成立しました。
国土交通省は、「美しい国づくり」のために「襟を正す」と宣言し、量から
質への転換の必要性を強調しています。
景観についての私の関心は、ひとつは街路樹の整備です。
多分、仙台は街路樹の整備では日本の先端を走っているでしょう。
.jpg)
もうひとつの関心は、電線の地中化です。
日本は先進国の中で最も遅れているようです。
今後数十年間の大事業として取り組むべきテーマだ
と思います。
仙台も、地中化については十分とは言えません。
青葉通りから一筋奥に入った通りでは、依然として
蜘蛛の巣(電線)がはびこっていました。
景観についての私の想いを、近いうちにまとめてみたいと考えています。
仙台は、そのためのひとつの検討事例として、もう一度ゆっくり散策してみ
たい街だと思いました。
(散策:2006年 6月27日
~ 6月30日)
(脱稿:2006年 7月12日)
------------------------------------------------------------------
この記事に
感想・質問などを書く・読む ⇒⇒
掲示板
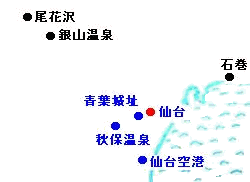
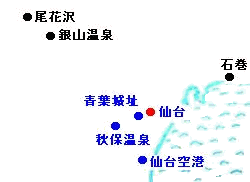
飛行機にした理由は、神戸空港です。 今年(2006年)2月16日開港の空 港を覗いておきたい、と思ったためです。 ←神戸空港マリンエア ↓幼稚園の子供たち
JRの最寄り駅は三宮で、三宮から空港までは無人運転のポートライナー で20分でした。滋賀県からのアクセスは割合スムーズです。 航空券はインターネットで予約しました。28日以前予約割引+チケットレ ス割引で、片道11,100円でした。意外なことに、名古屋空港からより も、神戸からの方が片道100円安いのでした。 3.青葉城址 仙台空港からバスでJR仙台駅まで40分でした。 この日は青葉城址を訪ねる予定だったため、仙台駅の案内所で尋ねたところ、 「ループル仙台」というレトロ調のバスが巡回していることが分かりました。
ループル仙台は、晩翠草堂から始まる 市内の観光スポットを、一周1時間で巡 回しています。1回250円、1日乗り 放題は600円です。 ←ループル仙台 ↓晩翠草堂(晩翠が晩年を過ごした家)
青葉城は、関が原の後に60万石に封ぜられた伊達政宗が築いた城です。 現在、城はなく、城址だけです。 本丸の石垣は、ヨーロッパの城壁などに見られるように、四角に加工された 石で隙間なく積み上げられていました。「最近仙台市が修復した」旨の案内 を見かけたので、つまらないことをするものだ、と一挙に興ざめしました。
しかし、修復作業の展示現場の担当者に聞いた ところ、この石垣は昔からの石を、そのまま積み 直しただけなのだそうです。 ←伊達政宗の像 ↓加工された石を積み上げた石垣
城跡の公園には、土井晩翠の像がありました。 「荒城の月」の作詞者として名高い晩翠は、明治4年(1871年)に仙台で 生まれ、昭和27年(1952年)に晩翠草堂で亡くなりました。
←土井晩翠像 島﨑藤村の詩碑がありました。 明治5年(1872年)生まれの藤村は、明治 29年(1896年)、25歳のときに東北学園 へ英語教師として赴任し、「草枕」の詩を書き上 げたそうです。 ↓藤村の詩碑
青葉城址は青葉山の上にあり、名前のように青葉に囲まれていました。 上空から眺めたら壮観だろうと思いました。
そこで、清水から飛び降りる思いでヘ リコプターをチャーターし、上を飛んで みました。左端に上の写真の石垣が見え ます。 チャーター費用はどれ位か、など興味 のある方は こちら をご覧ください。 ↑上空から見た青葉城址 青葉城址を見学した後、友人3人と仙台駅で合流しました。 京都と名古屋からの友人はフェリー、東京からは新幹線で来ました。合流し た後、人気のあるホルモン焼き屋に行き、店の外で1時間待ちました。 腹ごしらえをした後、4人でゲームを楽しみました。 4.銀山温泉 翌日、私は友人に会うため、一人で山形県の尾花沢市に行きました。 仙台から新庄行きの48ライナーという特急バスが出ていました。48号線 を走るバスです。バスの最前列に座って景色を眺めていたら、あっという間 に1時間50分が過ぎて尾花沢に着きました。 バス停で友人が待っていました。 私が東京で勤務したときの友人で、40年振りの再会です。友人の家はバス 停のすぐ近くでした。仙台は涼しかったのに、ここはむっとする暑さでした。 「山形は暑いんだよ。ここは冬には2-3メートル雪が積もるしね」と友人 は東京にいたときよりもやや強い東北弁で言いました。 友人が連れて行ってくれたのは銀山温泉です。
ここは江戸時代の初期に銀山として栄え、 寛文11年(1671年)頃に閉山となった後、 温泉地として発展してきたそうです。 ←手掘りの坑道跡
温厚な友人は土地の開発事業などにも関わっ てきたため、顔が広い様子でした。 友人が親しくしている土産物屋さんに入って みると、昔の温泉街を撮った写真が掲載されて いました。
←大正時代の温泉街(江戸屋さん掲示) ↓現在の温泉街
.jpg)
銀山温泉は、木造3階建ての旅館が有名です。 かつては「おしん」のロケ地として、近年はアメ リカ人女将(ジニーさん)が知名度を上げるのに 寄与しています。 ←木造3階建ての旅館 ↓アメリカ人女将の旅館(建替え中)
友人は不動産関係の仕事をし、地道に自分の居場所を固めてきたようです。 山形の蕎麦膳をご馳走になり、温泉で汗を流しました。 家族と友人宛にさくらんぼの宅配を手配して、仙台に戻りました。 夕食を済ませてからマンションに戻ると、名古屋からは飛行機、横浜から は新幹線で、友人が二人来ており、熱戦が進行していました。 5.石巻(いしのまき) 今回は6人が合流しましたが、夜以外は全員で行動することはありません。 ご開帳となる夜だけがコアタイムで、昼は自由です。 翌日、2人は山形へさくらんぼ狩り、私を含む4人は石巻へ出かけました。
松島を横目にしながら、JRで約1時間半で 石巻へ着きました。 ←松島の一部(電車から)
石巻には、萬画家石ノ森章太郎さん の「石ノ森萬画館」があり、萬画の国 をうたい文句にしています。 (「萬画」とは、ジャンルを問わない 作品を量産した石ノ森さんの造語で、 「漫画」を越えた表現ツールである、 という意味のようです) ←JR石巻駅 石ノ森さんの生家がある登米市(中田町石森)は、石巻の少し北です。 (なぜ石巻が張り切っているのかは分かりません) 関西は梅雨空がぐずついていたのに対し、私たちを迎えくれた東北は晴れ が続きました。とりわけこの日は雲ひとつない快晴でした。 しかし、この日の行程は、テポドンを打ち込まれた以上に悲惨でした。 この日の目的は、石巻漁港にある食堂で新鮮な海鮮料理を食べることでした が、着いたのが漁港の食堂としては少し遅かったため、めぼしい料理はすべ て売り切れだったのです。今回の仕切り役は、賭○で生計を立てている組長 です。この組長は、麻雀や碁で、私のような善良な市民からなけなしの小銭 を巻き上げて生活の足しにしている悪役です。 その組長が、朝ドラ見たさに出発時間を遅らせたのが原因でした。 その上、足の悪い仲間にお構いなくスタスタと先導した組長が道を間違え たため、漁港の周りで往復1時間以上も炎天下を歩かされました。名古屋か ら来た一人は膝と腰の痛みに顔をゆがめていましたが、帰ってからは病院通 いをしているとのことです。 この日は石巻へ往復し、ありきたりの定食を食べただけで終わりました。 6.秋保(あきう)温泉 翌4日目の最終日の朝、3人は所用で帰りました。 残ったのは組長と、組長の指示通りに忠実に動いたり、ときには組長に強く 意見をしたりする若頭(還暦間近)と、私の3人です。 この日は、年寄りらしくおとなしく温泉に浸かって過ごそう、ということに なりました。
仙台からバスで1時間ほどの近距離に、秋保 (あきう)温泉があります。 かつて、伊達家の湯治場が置かれたそうで、 有馬、道後とともに、日本三名湯のひとつに数 えられているそうです。 ←名取川
自然公園のある湯に陣取りました。 露天風呂付きの温泉に浸かった後は、ゆ ったりと蕎麦を楽しむことができます。 (食事と入浴のセットで1,575円)
灯篭あり 岩の間を走る水あり
足湯あり(2箇所)
広い池あり
いくつもの花園あり、..。ゆっくり見てまわるのには30分以上はかか りそうな、広い起伏のある庭園が広がっていました。 いつも碁盤を抱えてくる組長ですが、この日は手ぶらでした。 この日の朝帰った1人は組長の先輩で、日本棋院6段の猛者であるため、い つものような元気を失くしたのかも知れません。 7.おわりに 杜の都と呼ばれている仙台は、緑一杯に包まれていました。 周囲の山々だけでなく、あちこちの街路樹の緑が街を包みこんでいます。 緑を見て気付いたのは、松、杉、檜などの針葉樹が見当たらず、ほとんどが 欅などの広葉樹だということです。
青葉城址からバスで仙台駅に戻るとき、街路 樹が道路を覆っている光景に感動し、思わずバ スを降りてしまいました。 いつだったか、ドイツのデュッセルドルフを 歩いたときの感動が蘇ってきたのです。 道路が欅のような巨木の緑に包まれ、ゆったり とベンチに憩う人の姿が印象的でした。 ←定禅寺通りの街路樹 2004年に「景観法」が成立しました。 国土交通省は、「美しい国づくり」のために「襟を正す」と宣言し、量から 質への転換の必要性を強調しています。 景観についての私の関心は、ひとつは街路樹の整備です。 多分、仙台は街路樹の整備では日本の先端を走っているでしょう。
もうひとつの関心は、電線の地中化です。 日本は先進国の中で最も遅れているようです。 今後数十年間の大事業として取り組むべきテーマだ と思います。 仙台も、地中化については十分とは言えません。 青葉通りから一筋奥に入った通りでは、依然として 蜘蛛の巣(電線)がはびこっていました。 景観についての私の想いを、近いうちにまとめてみたいと考えています。 仙台は、そのためのひとつの検討事例として、もう一度ゆっくり散策してみ たい街だと思いました。 (散策:2006年 6月27日 ~ 6月30日) (脱稿:2006年 7月12日) ------------------------------------------------------------------
この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ